幼い頃、ボンヤリさんの私を心配した両親が、学研の科学と学習を購入してくれたのが、動物や自然に興味を深めたきっかけでしょうか。
もともと当時は見渡す限りの田園地帯で暮らしていて、母が世話する小さな庭がある家で育ち、小さい動物や虫はたくさんいましたし、図書館や貸本屋が好きでしたが、毎月必ず自宅に届く本として楽しみにしていました。付録で実験するのが好きで、のちには子育て中も楽しみました。
図書館や本屋さんで、写真集や本を眺めては他の国の不思議な植物や生き物の話題は夢中になって読んだり。小学生から中学生に至る頃には、星新一さんの短編SFに夢中になっていたことも思い出します。
そんな中でも幼心に、人間とそのほかの動物たちは、明らかに違うなと感じるようになりました。ヒトは、環境をヒトのために変えていく。他の動物たちは、環境に順応しようとします。
何もかも受け入れているように見える動物たちのことを、人間を超えられない存在だと思っているかもしれない人間。上から目線です。
相容れないこの生き物の関係性は、どんなふうに地球を変えていくのだろうと想像しました。
私が子育てを始めた頃には、絶滅危惧種に関する記事が多くなりました。さらに、生き物たちがこの星の循環を自然に保ってきたのだということを教えてくれる情報は増えていく一方で、その環境が壊れていく報道も多くなりました。代わりになる生き物はいないから、一つの固有種が消えるたびに、世界中は急速に環境を変化させていきます。
誰にも、それを止めることができないのなら、せめて、人権を重んじる心が必要なように、生き物すべてを尊重する気持ちを持ち続けたいと思いました。
小鳥と生活していた事がありますが、意思の疎通に必要なのは、共通言語だけではないということを強く感じました。
動物たちを思いやることで人が変わると思い続けてきましたが、動物たちと関わる人たちが変わると、動物たちも変化していくように思います。
そうこうしているうちに、私は、虫や寄生虫にいたるまで、興味はつきることがなく、お話に出てくる動物たちと、実際に生きている動物たちとの登場人物の関係性も考えるようになりました。
もしかしたら、自分=人間、その人間以外の動物に対する偏見や軽視は、他の国の人たちや世界のいろいろな生き方をしている人たちに対する考え方にも通じるのではないかと思うようになりました。
だからこそ、私は、これからの子供たちにこそ、たくさんたくさん、自分たち以外の動物や虫や生物のことを、もしかしたら、まだ出会っていないかもしれないような動物のことを考えてほしいと思います。
植物園や大きな公園も大好きなので、もっぱら草花などの種を集めて育てたりしています。野菜を作れるくらいに余裕が生まれたらうれしいと思います。
動物園が好き
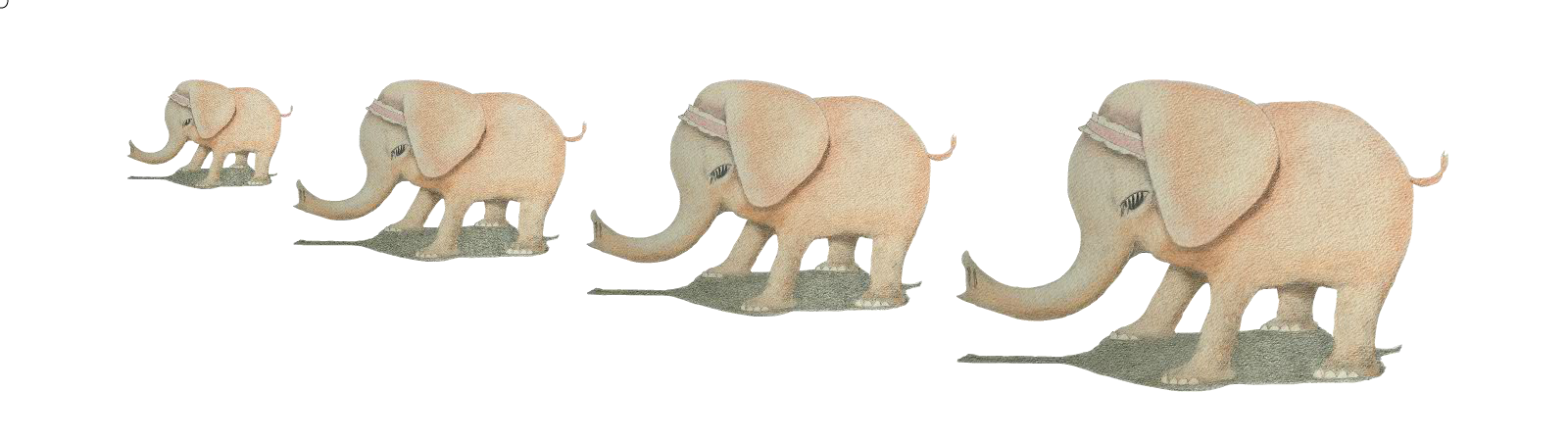
2020年、新春から新型コロナウイルスが世界中に広まり、人の生活は一変しました。困惑、それとともに、変化することを受け入れる速さにも驚きます。
というより、準備されていた世界なのかもしれない、と思います。
それでなくても、変化著しいのですが、2020年新型ウイルスで加速した社会の変化のスピードは、今まで多くの人たちが積み上げてきたものを一瞬でノスタルジックな過去に変えてしまうような不安がありました。
人の生活は落ち着きの良い各々のスタイルを探して、迷走しているようです。
2023年春からウイルス対策も緩和されて通常の生活に戻ると共に、堰き止められていた流れが押し寄せるように、長い間覆い隠されてきた多くのものが白日の下に晒され、痛ましさや忌まわしさが極まる混沌とした報道に心が乱される日々です。
人の生き方や平和や経済がいろんな風に歪んで、何を観ても地球儀の軸が曲がって見えるかのような世界です。私の人生の中でも本当に大変な時代になったと実感するようになりました。
おそらく、そんな中動物園も水族館もさらに変化していくだろうと思います。
実は、動物園や水族館に行くようになったのは大人になってからです。
きっかけは、なんとなく疲れたなあというときに、動物園で一人ぼんやりしてみたことでした。子育ての間も、幾度となく動物園に行きました。
動物たちはみんな、どう過ごしているかなあ、という感じです。子どもたちに見せたい、ということは勿論ですが、自分自身にも投影する思いとして、置いてきぼりにしてはいけないものを確かめに行くという気持ちでした。。
ひところは、閑散とした園内で動物たちがひっそりと取り残されているような気がしました。
そのうちに、代は変わって、生まれた時から人間と接している動物たちが増えた今、子育てが上手にできない動物さんたちが増える半面、本来どのように動物たちが生きているのかを知らされるようになったように思います。
動物園にいる動物たちが、遠くの国から連れてこられた運命に対して大きな矛盾があるけれども、動物園や水族館のような存在が果たす役割は、私が幼かった頃より益々大きくなったと感じます。
動物園の動物たちも高齢化して、日々、亡くなっていく命もあれば、育てやすい環境の動物園にお引越しをしたり、もうすでに何代も動物園で生まれ育っている種もあります。今では、少しでも環境をよくし て、動物たちに幸せに過ごしてほしいという施設の方々の発想や努力が生かされるようになったと感じます。環境が変わると動物たちの様子も変わってきたように思います。そもそも自然界では生きられなくなっている動物たちもいます。今では保護する役割も担っている施設だと思います。
ちなみに、いまさらですが動物園の起源をwikiで調べたところ、どうやら、シェーンブルン宮殿の動物園が初めて一般公開された動物園かもしれない、という情報に出会い、私の数少ない海外体験の一つであったことが驚きです。
そうすると何年前からあるのだろうか。。日本では、1882年上野の動物園が始まりらしいです。思いのほか歴史が長いのでこれも驚いてしまいました。
そんなわけで、動物園を歩くときは、辛いことも多かったであろう、ここにいてくれてありがとうという気持ちで見てまわります。大変苦労の多いことでしょうが、どうか動物たちの環境が守られていくように、お手伝いできることを考えたいです。と言ってもこんなことを書くことくらいです。
動物園のまわりぐるりをのんびり歩くのも楽しいです。
塀の外からも、垣間見える裏方の魅力があります。

ゾウさんペーパーに描いた、男の子の絵
水族館が好き
久方ぶりに江ノ島水族館に行った時の思い出。
リニューアル前で割引がありました。あおりいかさんの優雅さは、いつもピカイチです。背が光っているのが幻想的です。
コブダイさんが一番のイケメン魚でした。じーーーっと見ていると岩の影に下がって、暗いところから、じっとこちらを見ていますが、青く光る眼がすごくきれいです。4月の後半には、ウミガメさんの新しいブースができてウミガメの赤ちゃんに会うことができました。
水族館といえば、私が大好きなのは、クラゲとピラルクです。
クラゲは、はかなげで幻想的でありながら生き物の生命力や怖さを教えてくれます。
ピラルクは、大きいものは、ど迫力に大きい淡水魚です.目を見張るのはその素晴らしいウロコです。靴べらにもされるくらい頑丈だということですが、ピラルクも現地では食されていることを知り、人はなんでも食べちゃうんだなあと感慨ひとしお。。
水族館は、現在では見せ方や楽しみ方が工夫されていて、美しくて不思議な世界です。本当に水の底にもぐったような感じ。空を飛ぶように悠々と泳ぐ生き物たちがすごいです。かなわない。
出展のときお話しできた作家さんの謎めいた生態の話で、ウミウシや磯の生き物たちの世界ももっと覗いてみたくなりました。磯遊びは大好きで、ヤドカリさんやヒトデさんを観察したのが楽しかったです。歳とともに、水や森林や空や、自然の中に還っていきたい自分を感じます。

